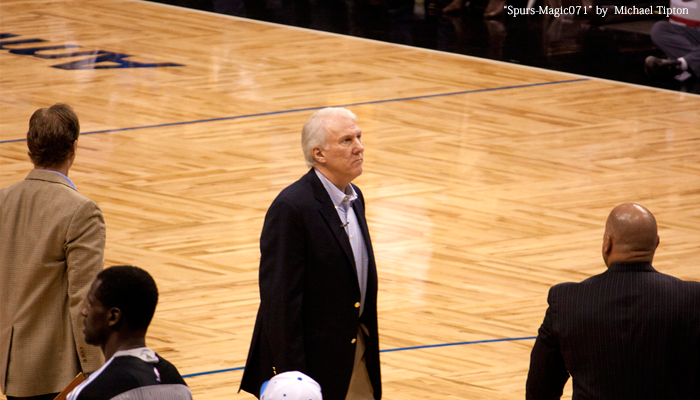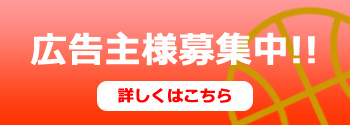デレック・フィッシャーとバスケットボールの正しいやり方
優勝11回という偉業を成し遂げたフィル・ジャクソンの率いたチームには、数々のNBA史に残るスーパースターがいました。ジョーダン、コービー、ピッペン、ロッドマン、シャック。彼らがいなければ、確かにフィル・ジャクソンの偉業が成し遂げられられることはなかったかもしれません。
ただ、同時に、フィル・ジャクソンがヘッドコーチに就任する以前には、当時のブルズもレイカーズも、スーパースターを有しながらも優勝に手が届いていなかったのもまた事実です。では、ブルズやレイカーズでジャクソンが行った変革とは一体何だったのでしょうか。ここでは、『イレブンリングス 勝利の神髄』で紹介されている様々なプレイヤーたちとのエピソードを交えて、その秘密に迫ってみようと思います。
その最初として、まず今回はロサンゼルス・レイカーズで(他にはウォリアーズ、ジャズ、サンダーなどで)ガードとして活躍したデレック・フィッシャーを取り上げます。

By Keith Allison [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
様々なプレイヤーたちがいる中で、フィッシャーを最初に挙げるのには理由があります。ひとつにはもちろん、フィル・ジャクソンが現球団社長を務めるニューヨーク・ニックスにおいて、来季のヘッドコーチとして招聘されたのがデレック・フィッシャーだったからです。そしてまた、ジャクソンのバスケットの中では、特定の役割をこなすロールプレイヤーがスーパースターと同じくらいに重要視されており、その筆頭となるのがフィッシャーだからです。
(デレック・フィッシャーのキャリアハイライト映像)
このフィッシャーを、ジャクソンは本書の中でこのように評しています。
私がコーチをしてきた多くのプレイヤーは、記録の上では平凡なものだろう。しかし、自分自身に合った役割を作り出させるというプロセスの中で、彼らは恐るべき戦士へと成長するのである。
デレック・フィッシャーが良い例だ。彼は足の速さとシュートスキルが平均レベルであったため、レイカーズの控えのポイントガードとしてスタートした。しかし、彼は疲れを知らずに動き回り、自分自身を逆境でこそ力を発揮するかけがえのないパフォーマーへと変化させた。そして、私が今までコーチをしてきた中でも最高の選手の1人となったのである。(26頁)
「記録の上では平凡」と語りながらも同時に「最高の選手の1人」との評価を与えることは、華やかな個人技が称賛されるNBAにあっては珍しいことかもしれません。しかし、ジャクソンは随所でこうしたロールプレイヤーたちへの称賛を口にします。例えば、シカゴ・ブルズが後期3連覇を成し遂げたシーズン最後の祝勝会では、ジャクソンが乾杯を捧げたのはジョーダンでもピッペンでもロッドマンでもなく、ロン・ハーパーでした。
そこで、各人が、チームの誰か他のメンバーのために乾杯をした。私はロン・ハーパーに賛辞を送った。オフェンスで輝くスターから、ディフェンスのスペシャリストへの転換という私心なき行動を讃えてのことだ。それにより、チームは2回目のスリーピートのために走り出す準備を整えることができた。(219頁)
後期3連覇を成し遂げた原動力のひとつとしてジャクソンは、ハーパーをガードに据えたことを挙げています。198cmという長身選手をガードに起用することで、どのポジションからでもシャックのような大型センターにトラップをかけられる状況が整った、と。さらに、ジャクソンは、レイカーズのヘッドコーチに就任した際にも、ブルズからロン・ハーパーを呼び寄せ、チームの下支え的な存在として頼りにしていました。
このように、ロールプレイヤーに重きを置くフィル・ジャクソンですが、その中でもフィッシャーに対する信頼は強いものがあります。とはいえ、その信頼とは、盲目的にフィッシャーを起用するという形で現れるのではなく、フィッシャーが「チームのための最善の行動」をしてくれるだろうという信頼であり、その「最善の行動」の中には「必要があればベンチに下がる」ということすら含まれています。例えば、2003-04シーズン、レイカーズがゲイリー・ペイトンを獲得したときのこと、
2003-04年シーズンの始め、先発を外れて、ゲイリー・ペイトンにその役を譲るよう頼んだときも、フィッシャーは何の不平も言わず承諾してくれた。しかしながら、シーズンが進むにつれて、私は彼のプレータイムを増やしていった。特に、際どい勝負のときには。フィッシャーがフロアにいると、オフェンスはまさしくよりスムーズに流れるのだ。(317頁)
また、レイカーズが最後の二連覇を達成する前年度、他チームに移籍していたフィッシャーが戻って来たことで躍進の準備が整ったのですが、このときも、ジャクソンはフィッシャーを共同キャプテンに任命しながらも、控えのジョーダン・ファーマーを20分以上出場させることを提案し、フィッシャーはそれに賛同しています。結果として、フィッシャーとジョーダン・ファーマーは2人で合わせて平均20.8得点をあげました。
「チームのためにプレーをする」というのはしばしば言われることですが、本当に難しいのは「チームのためにプレーをしない」ことなのかもしれません。ジャクソン自身、控えのプレイヤーだった時代が長く、そのことを何よりも理解しています。
バスケットボールにおいては、コーチを嫌っている者は大抵、自分にふさわしいと思っているプレータイムをもらっていないプレイヤーだ。私自身も控えであったので、重大な試合の最中にベンチで無視されようものなら、どれほどむしゃくしゃするものか知っている。(108頁)
ジャクソンが最高のチームプレイヤーであると認めるピッペンでさえ、セットプレーのラストシュートを打つ役をクーコッチに奪われた際には、ふてくされて試合に出ないという行動に出たことがありました(157-8頁)。かといって、このような選択ができるのは、フィッシャーが自分に自信がないからというわけではありません。フィッシャーはプレッシャー下での3ポイントシュートに定評がある選手であり、コービーからもその精神的な強さを尊敬されていたといいます。
(フィッシャーのクラッチプレーBEST5)
フィッシャーはただ、ジャクソンが常々語っている「バスケットボールの正しいやり方」を何よりも重要視していたのでしょう。本書の中で、フィッシャーは「正しくプレーをすれば、私たちは途方もなく良いチームになれる」(315頁)と語っています。
では、この「バスケットボールの正しいやり方」とはどのようなものでしょうか。本書を通じて何度も登場するこの言葉。それは、フィル・ジャクソンが自らの師であるニューヨーク・ニックス時代のヘッドコーチ、レッド・ホルツマンから学んだことでした。
彼(レッド・ホルツマン)が信じていたのは、正しいやり方でプレーをするということである。それはつまり、オフェンスではボールを動かし、ディフェンスでは激しいチームディフェンスを行なう、ということだ。レッドは、5人でのプレーが1on1の創造性に比べて遙かに広く浸透していた時代、ジャンプシュートが開発される以前にバスケットボールを学んだ。(41-42頁)
(レッド・ホルツマンが率いた1973年ニックスのハイライト映像)
それを実現するためのルールとして、レッド・ホルツマンはシステムやセットプレーを信奉するのではなく、単純な2つのルールを常に課したと言います。ディフェンスにおいては「ボールを見ろ」。オフェンスにおいては「オープンな味方にパスを回せ」。あまりに単純なこの2つのルールですが、この2つは、それぞれがジャクソンのバスケットボールの精神に通じています。
ボールを見ろ。(中略)レッドの考えでは、気づくことこそが良いディフェンスの秘訣だった。彼はいつでもボールから目を離さないということと、そして、今まさにフロアで起こっている物事を敏感に察知し溶け込むことを強調した。(42頁)
オープンな味方にパスを渡せ。もしレッドが今日コーチをしていたら、彼はバスケットボールがいかに自己中心的になったかに唖然とするだろう。彼にとって、無私の精神(セルフレスネス)はバスケットボールにおいて不死を授ける聖杯だった。(43頁)
ジャクソンのバスケットボールにおいては、この2つのルールは明示的なルールとして現れるのではなく「ボールを見ろ」は「仏教的な気づき(マインドフルネス)」として、「オープンな味方にパスを回せ」は「無私の精神(セルフレスネス)」として、それぞれがジャクソンのバスケットボールを支える骨子になっています。そして、ジャクソンのバスケットボールにおいては、「仏教的な気づき(マインドフルネス)」を促す手段として瞑想を取り入れ、「無私の精神(セルフレスネス)」をオフェンスで実現するためにトライアングル・オフェンスというシステムを導入しています。
では、フィッシャーのバスケットボールはどうでしょうか。フィッシャーはジャクソンから、「これまでコーチをした中で最も無私欲(セルフレス)なプレイヤーの1人だ」(317頁)と称賛されるプレイヤーであり、彼自身は、自らのバスケットボールをこう語っています。
自分はシュートをたくさん打ちたいですが、誰かがオフェンスを動かさなければならないし、しかもそれをするのはコービーやラマーということにはならないでしょうから、自分としては、自分に回ってきたシュートチャンスをしっかりと決めなければならないと確信していました。(318頁)
そこには、自分の役割に対する冷静な分析があり、そして、レッド・ホルツマンが言った「オープンな味方にパスを回せ」という無私の精神の遺伝子が、デレック・フィッシャーに受け継がれていることがわかります。
また、フィッシャーはその場を察知し、適切な行動を取ることができる能力にも長けており、そのことは、フィッシャーのチームメイトへの接し方によく現れています。
フィッシャーがレイカーズに戻って来たとき、彼はすぐに気がついた。自分とコービーは、最初のスリーピートのときにチームにとってうまくいっていたスタイルとは異なるスタイルのリーダーシップに順応しなければならない、と。チームには、他に優勝を経験したベテランは残っていなかった。ロン・ハーパーもジョン・サリーも、ホーレス・グラントも。だから、フィッシャーは、若く経験不足なロスターたちに気持ちを通じさせたいと思うなら、自分とコービーは相手の立場になって考えなければならないと悟ったのだ。「私たちは、1000mの高さからチームを引っ張ることはできません」現在、フィッシャーはそう語る。「私たちは海抜0mまで戻ってきて、あいつらと共に成長しようとしなければなりません。そして、そのプロセスが起こったならば、私たちは真の関係性と兄弟愛を感じ始めるのです」(318-9頁)
これは、「ボールを見ろ」というルールで表現される試合中の気づきとは異なりますが、フィッシャーの「仏教的な気づき」を端的に表しています。
このように、フィッシャーはレッド・ホルツマン、フィル・ジャクソンと受け継がれてきた「バスケットボールの正しいやり方」を体現するようなプレイヤーだったことが分かります。だからこそ、ジャクソンはニックスのヘッドコーチとしてコーチ経験のないフィッシャーを据えることを決めたのでしょう。
この記事の著者
- 上智大学哲学研究科特別研究員
-
1981年川崎市生まれ。現在、上智大学哲学研究科特別研究員(専門はギリシア哲学・倫理学)、日本バスケットボール学会理事。2005-07年には、上智大学男子バスケットボール部アシスタントコーチを務めた。
主な訳書
マイク・シャシェフスキー著『コーチKのバスケットボール勝利哲学』(イースト・プレス)
同著『ゴールドスタンダード 世界一のチームを作ったコーチKの哲学』(スタジオタッククリエイティブ)
アダム・フィリッピー著『バスケットボール シュート大全 プロスキルコーチが教える「シュート」のテクニック・ドリル・方法論』(同)
ジョルジオ・ガンドルフィ編『NBA バスケットボールコーチングプレイブック』(同)
フィル・ジャクソン著『イレブンリングス 勝利の神髄』(同)
この著者のほかの記事
 コーチング2015.04.30名将ボブ・ナイトから学ぶコーチングのための34のヒント
コーチング2015.04.30名将ボブ・ナイトから学ぶコーチングのための34のヒント コーチング2015.02.01【NCAA通算1,000勝達成】コーチKの歩みと言葉を今一度ふり返る
コーチング2015.02.01【NCAA通算1,000勝達成】コーチKの歩みと言葉を今一度ふり返る コーチング2014.07.29デレック・フィッシャーとバスケットボールの正しいやり方
コーチング2014.07.29デレック・フィッシャーとバスケットボールの正しいやり方 コーチング2014.06.23フィル・ジャクソン新たなる旅路へ −ロード・オブ・ザ・”イレブン”リングスを振り返る−
コーチング2014.06.23フィル・ジャクソン新たなる旅路へ −ロード・オブ・ザ・”イレブン”リングスを振り返る−